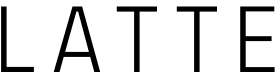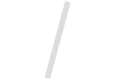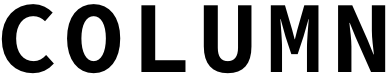「ほめて伸ばす」しつけは、言い方に注意!子どものやる気を引き出す褒め方のコツ
こんにちは、数教研の米田淑恵です。
よく「子どもはほめて伸ばしましょう」という本や記事を見かけると思います。
特に最近、教育関係の本や子育て本などで、頻繁に使われています。
塾などでも「ほめて伸ばす」をモットーとして掲げているところもあるでしょう。
この「ほめて伸ばす」というと、どんなことを思い浮かべるでしょうか?
例えば、お手伝いをしてくれたときや勉強を頑張った時、人に優しくできたときなど、保護者様の価値観に応じて様々なシーンが考えられるでしょう。

勉強に関して「ほめて伸ばす」ことを考えてみたとき、やはり「テストの点が良かった」「100点を取った」など、わかりやすい指標があるかもしれません。
しかし、この結果をほめることは、実は子どもにとって、さほど「伸びる」ことと繋がらないようなのです。
例えば、お子さんが漢字テストで100点をとったとします。
お父さんやお母さんはもちろん「よくできたね」と声をかけるでしょう。
お子さんは「ぼく(わたし)はできるんだ」という気持ちになれますね。
しかし、毎週行われる漢字テストで「よくできた」を続けていると、お子さんはこの程度でほめてもらえるのだと認識してしまうのです。
その結果、より難しい問題へ取り組むのを嫌がったり、やってもすぐに「できない」と言ってしまうようになってしまうのです。
親から見れば「ほめて伸ばす」はずだった声掛けが、逆効果となってしまうわけです。
反対に、親御さんがテストを見ても、特に反応しなかった場合はどうでしょう?
この場合は、子どもはほめて貰わないのですが、親がどの程度で「ほめる」のかも知らないままのため、少しチャレンジな問題でもとりあえず解いてみるようになります。
しかし、お子さんは「できた」感は感じることはできなくなります。
では、どうほめるのが良いのでしょう?
先ほどの漢字テストで100点をとったケースであれば、100点をとったという結果ではなく、テストのためにしっかり勉強した努力の過程をほめてあげるとよいのです。
お子さんはお父さんやお母さんからほめてもらい、達成感を味わいます。
しかし、ほめられたのは100点の漢字テストなのではなく「頑張った自分」に対してですから、次ももっと頑張ろうという気持ちになるのです。
その結果、ちょっとこれは難しいなと感じる問題でも「がんばってみよう」という意欲が湧くようになります。
この意欲こそが本当の意味での「ほめて伸ばす」ことなのです。
ただむやみやたらにほめるのが良いのではないのです。
これはもちろんお手伝いをしてくれたときも同じです。
お手伝いした結果、お母さんが望むレベルに達していないこともあるかもしれません。
ですが、お手伝いをしようと思った優しい気持ちや努力をほめてあげると、子どもは「次もお母さんのお手伝いをしよう」という気持ちになれ、結果としてお母さんが希望するお手伝い内容を段々とできるようになっていくのです。
私たちは、とかく結果を重視してしまいがちです。
しかし、子育てにおいては、勉強やしつけも含めて「ほめる」点に気を付けてみると、お子さんの伸びが違ってくることは間違いありません。
どうせなら正しい「ほめて伸ばす」をためしてみませんか?
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

こんにちは。
数教研千里中央教室の米田です。
豊中市・千里中央の新千里西町会館にて、週2回皆さんと楽しく学習しております。
子ども達の「わかった!」という言葉を聞くのが何よりうれしいです。
ブログも毎日更新中です。一度のぞいてみてください。「数教研千里中央教室へようこそ」で検索。
|
|
|