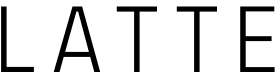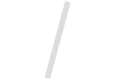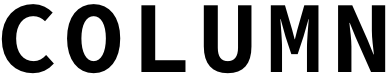子供に依存する「毒親」の心理と特徴!毒母には”対抗”より”話し合い”で対処して
子供に過干渉する「毒親(毒母)」について解説。毒親の特徴と、毒親育ちの子供に見られる悪影響、自分の親が「毒親」だと気づいたときの対処法などを紹介。
こんにちは、 メンタルケア心理士の桜井 涼です。
フジテレビ系ドラマ『嫌われる勇気』第三話をご覧になりましたか?
典型的な「毒母」と呼ばれるタイプの母親が出ていましたね。
毒親(毒母)は、子どもに依存する心が強く、子どもの人生を自分の人生のようにコントロールしようとするところがあり、子どもの成長過程において良くありません。
そのあたりを詳しくみていきましょう。
毒親・毒母は、過剰に子どもに依存して、子どもの全てを自分の思い通りに動かそうとする親のことを指します。
自分が叶えられなかった夢や諦めてしまった進路などを、子どもを介して叶えようとするといった行動を取ります。言わば、子どもの人生を自分の人生とリンクしているように考えてしまうのです。
そのため、過干渉になり、全てのことにおいて先回りをしてしまいます。
こういう親の場合、決まって「私はこの子のためを思ってやっている」という言葉を発して、自分のやっていることを正当化しようとします。
考え方が支配的になっているため、常に自分が主体です。
毒親・毒母チェック!
毒親・毒母の特徴として、例えば次のような考え方や行動が見られます。
☑ 子どもの人生は、私が何とかしなきゃと思っている
☑ 子どもに尽くすことだけが生きがいになっている
☑ 過剰に子どもに手をかける(高学年になっても着替えを出す・学校の準備をしている等)
☑ 外からの評判を気にするため、良い母に見られるようにしている
☑ 自分の気分次第で、子どもを平気で罵ったり、手をあげたりする(しつけ・この子のためと理由付けしている) など
一見子どものことを考えて行動しているように見えますが、どの場面においても、子が主体ではなく、親が主体となっています。
毒親・毒母は、子どもに依存し過ぎてしまう傾向があります。
それには、さまざまな背景が存在しています。
夫婦仲が良くないことや、少子化、自分が叶えられなかったことを叶えてほしいなど、思いはさまざまです。
そのため、「あなた(子ども)のためなのよ」と言いながら、支配的な言動が出てくるようになり、子どもの心に大きな影響を与えることがあります。
- いい子症候群になってしまう
- 常に親の目を気にして無理をする
- 失敗の経験がないので、打たれ弱くなる
- いつもビクビクしていている
- 親の言う通りにしないと愛してもらえないと思ってしまう
- 自己肯定感が異常に低い(人の顔色をうかがうようになる)
- 大きくなるにつれて、「居場所がない」・「家に帰りたくない」と思うようになる など
また、子どもが成長する過程で学んでいかなければならない、社会性やさまざまなことに対する耐性が身につきにくくなってしまうということも、覚えておかなければならない重要な点です。
親は、一生懸命に子育てをしているため、自分が子どもに対して依存的であることや、過干渉になってしまっていることに気がつかないことも多いのではないでしょうか。
子どもにおいては、年齢が低ければ低いほど親の愛情を求めるため、一生懸命に従おうとします。
自分の親が毒親であることなんて考えもしないでしょう。
そんな子どもたちが、自分の親が「毒親かも」と気づくのは、ある程度大きくなってきてからということが多いです。
自立しようとすると親が立ちはだかることに違和感を感じるため、気づくようです。
その時にできるのは、「親としっかり話すこと」です。
自分はどうしたいのか、どんな人生を歩んでいきたいのか、「自分の人生は親の人生とは別なんだ」ということを話さなければ、ずっと毒親・毒母のままです。
親も最初から支配的な毒親なわけではありません。
出産して育てていく課程で、夫婦仲の悪化や義父母からの圧力、第三者の目線、過去の自分との投影などさまざまなことで愛情のかけ方が違った方向に向いてしまっているだけなのです。
全部親が悪いわけではありませんが、子どもの成長過程に大きな影響をもたらしてしまうことは否めません。
家族や周りの人が気づいたら、声をかけてあげたり、子ども自身が気づいた時点で話し合いを持ったりすることが必要です。
気づかせてあげてください。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア
|
|
|