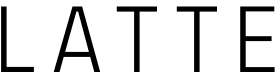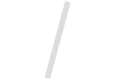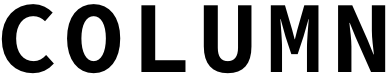「胃下垂」の症状と改善方法。食べても太らないけれど、下腹ポッコリの原因は?
腹筋を鍛えるのもいいけれど、東洋医学の視点から「胃下垂」症状や原因を見ていきませんか?効果的な漢方薬「補中益気湯」を紹介します。
こんにちは、薬剤師の田伏将樹です。
筋力の少ない女性や高齢者に多いと言われている「胃下垂」。
胃が正常な位置よりも下に垂れ下がっている状態です。
今回は、東洋医学の視点から胃下垂について考えていきます。

胃は、五臓六腑のなかの六腑のうちの一つ。
お腹のみぞおち辺りにある袋状の消化器官です。
アルファベットの「J」のような形をしていて、上は食道、下は十二指腸、小腸につながります。
口から食べたり飲んだりしたものは、食道を通って、まずは胃に納められます。
胃が元気であれば、胃から分泌される消化酵素と混ぜ合わさって、飲食物は小腸の方へ送られます。

ですが、胃下垂の状態になっていると、胃袋が伸びて張りがなく、食べ物を腸の方に送るという胃の本来の力が弱まっているため、胃の中に食べたものが長く留まったままになってしまいます。
そのため、食後の膨満感、胃もたれが続きます。
また、胃に食べ物がずっとあるため、胃酸がたくさん出てしまい、胃痛、胸やけを起こしやすくなります。
消化吸収の能力が落ちているので、人によっては太りたくても太れないという悩みもあるかもしれません。
生きている人の胃や腸などの内臓は、当然のように、あるべきところにあります。
ですが、例えば人体模型を作ってその中に内臓を配置しようと思えば、通常は重力があるので、何かで支えていなければ、各臓器は下に落ちてしまいます。
いつもは意識していませんが、人の各内臓には重力に逆らって、常に持ち上げている力が働いているのです。
内臓の場所を固定する力、垂れ下がらないように形を保持する力、これを東洋医学では「気」の機能の一つとして考えています。
消化器の「気」が不足すると、内臓を支える力が弱まり、その重力に耐えられなくなり、垂れ下がります。
胃に食べ物が入ってくることで重さが増すので、食後はさらに胃の位置が下に落ちてきてしまいます。
気が不足して内臓の位置が下がることを、「中気下陥」と言います。
西洋医学的には根本的な治療はなく、症状に応じて胃薬などが処方されます。
漢方では、消化器の「気」を増やすことで治療しようと考えます。
そこで、胃下垂の治療に処方される代表的な漢方薬が「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」です。
「中」はお腹の中心部分、つまり消化器のことであり、消化器(中)のはたらきを補って「気」を益す薬という意味です。
「気」を増やす生薬のほか、「気」を上に向かわせて臓器を吊り上げる力を助ける生薬が含まれていますので、胃下垂によく使われています。
また、子宮下垂、脱腸、脱肛(いぼ痔)なども、同じように「気」の不足によって垂れ下がった状態と考えられる場合があります。
「補中益気湯」は、胃下垂に限らず、臓器を持ち上げる作用のある薬だとすれば、病名は違ってもこれらの症状にも応用されることがある漢方薬です。
ただし胃下垂なってしまった場合、漢方薬だけですぐに元通りというわけにはいきません。
胃下垂の症状を和らげるためには、日々の生活で気をつけることも合わせて大切です。
☑ 食後、胃の出口が下向きになるように、体の右側を下にして休む
☑ 一度に食べ過ぎるのを避ける
☑ 普段から臓器の位置が正しい位置にあるように姿勢を良くしておく
☑ 筋力をつけるために適度な運動をこころがける
☑ 「気」を消耗しないように睡眠をしっかりとる
☑ 体を冷やさないようにする
ダイエットしたい方の中には、「太らないなんて胃下垂になりたい」と思った人がいるかもしれません。
ですが、憧れるのは間違いです。
太らない理由は、消化活動が弱まり、栄養を十分に吸収できないからです。
胃が正常に働いていないのです。
胃下垂は、病気であることを忘れないようにしましょう。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|