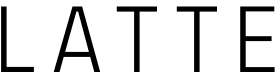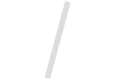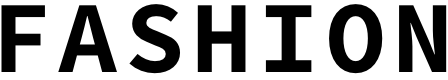仕事用の革靴はかかとに合わせよう!履き心地のよいビジネスシューズの選び方 (1/2)
こんにちは、パーソナルスタイリストの大竹光一です。
「仕事用の革靴を選ぶときに、どんな点に気をつけて選べばいいんだろう?」
こんなことを思ったことはありませんか?
”おしゃれは足元から”と言われるように、靴は見られることが多い部分です。

また、「足元をすくわれる」「足元を見る」という言葉はご存知ですよね?
それぞれ「隙を突かれて失敗する」「弱点や弱みを見る」という意味で、注意を払うべき部分が足元ということがわかります。
今回は、いくつかのポイントに分けて、ビジネスシューズ(革靴)の選び方をご紹介します。

以下が主な3つの製法です。
アッパーと表底を接着剤で貼り合わせ、加圧密着させる製法です。
構造がシンプルで、他の製法と比べて作業工程が短く、大量生産ができ、コストを抑えられるため、一般的に価格も安価です。

量産できるため色の幅も多く、軽く屈曲性に富むのが特徴ですが、底がスリ減ったときのソール交換は困難というデメリットがあり、実際に高級靴には、セメント製法はありません。
マッケイ製法の特徴はスマートな形、ソフトな足入れ、そして軽量です。
それは、甲革と中底と表底を一緒に通し縫いするという、比較的簡単なつくりのためです。

靴の内部の底から甲にかけて、足を包むように仕上げるため、まるで靴下のような感覚でフィットする靴として人気があります。
最近はそれだけでは判断できないものもありますが、靴の中をのぞき、中底の回りに縫い糸が見えるのはマッケイ製法の可能性が高いです。
またイタリアのスマートでドレッシーなシューズは、比較的このマッケイ製法が多いです。
この製法は、甲革や裏革等、甲の部品を縫い合わせて出来上がった「アッパー」と、「底」をジョイントする方法に最大の特徴があります。
中底につけられた 「リブ」と「アッパー」をすくい縫いした後、「中物」と「シャンク(靴の背骨となる心材)」を詰めてから、「表底」と「細革」を出し縫いします。

職人の技術が必要で、他の製法にはない「リブ」と「細革」がこの製法ならではの履き心地の良さの秘密です。
また、中物をタップリと入れられるために、長時間歩いても疲れにくいという長所があります。
それだけあって、高価です。
履きはじめは堅い印象ですが、履いているうちに足馴染みが良くなり、フィット感が高まります。
またソール交換が簡単なのも、特徴の1つです。
ビジネスシューズとしては、グッドイヤーウェルト製法が優れています。
というのも、革靴の中でも、工程やパーツが多く、丈夫です。
足に馴染むまでは少し時間がかかりますが、ソールの交換もできるので、長く履ける利点があります。
革靴の理想的なフィッティングは、「かかと」で合わせて、しっかり固定され、つま先に1~1.5cmのゆとり(捨て寸)を持たせると良いです。
よくつま先に合わせる方がいますが、そうすると、歩いて力が入ったときなどに、圧迫されたり、痛みを感じることに繋がってしまいます。
また、つま先にゆとり(捨て寸)を取るのは「ひも靴」の場合で、「スリッポン」や「ローファー」の場合は別です。
当然のことにはなりますが、その靴を履く際の靴下を着用してフィッティングするのが、ベストです。
その他のポイントとして、「足のむくみ」があります。
人が起きている時は、足が下になるために血流が足に行きやすく、上半身に行きにくいために、起きてから時間が経過すると、徐々に 足がむくんでいきます。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア
関連コラム
-
Fashion Latte編集部
|
|
|