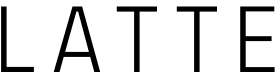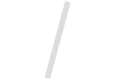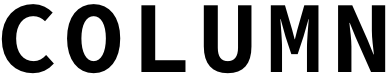ソフトクリームみたいな泡を飲もう♪ 沖縄伝統「ぶくぶく茶」の作り方
こんにちは、琉球茶道家の笠島香織です。
琉球茶道教授、ぶくぶく茶コーディネーターとして活動しています。
前回は、沖縄の伝統茶ぶくぶく茶の歴史や材料についてお話ししましたが、今回はぶくぶく茶の作り方、その中でも特に大切な泡の部分の作り方をご紹介します。

時間もかかり、プロセスも多いぶくぶく茶ですが、いちばん手軽に作れるレシピです。
コツがありますので、参考になさってくださいね。
まず最初にご準備いただくものは、「油気のない」フライパンもしくは鍋です。
ぶくぶく茶は油分を嫌います。
油分が入ると、肝心の泡が立たなくなってしまいます。
しっかり洗って、できれば熱湯を通しておいてください。
- 米 1/2カップ
- 茶葉 大さじ1杯
できれば2種類の茶葉を各大さじ1杯、なければ1種類を大さじ1杯でもOKです。
- 硬水 5カップ
コントレックス、フォルサーなどをご用意ください。
1. あらかじめ洗って水気をとっておいた米をフライパンに入れて炒ります。
焦げやすいのでゆっくりじっくりと、木べらなどで軽く混ぜながら均一に火を通します。
香ばしい香りが立ち、全体が濃いキツネ色になったら炒り上がりです。

ぶくぶく茶を1回分に必要な米の量は1/2カップですが、焦げつかずに均等に炒り上げやすい量は2カップ(4回分)~3カップ(6回分)です。
少量(1回分)の時は、特に火加減に注意してください。
2. 炒った米を、5カップの硬水で煮出します。
炒り米が充分にふくらみ、形が崩れるまで煮ます。

硬水はミネラル分の結晶が沈殿しがちです。
ミネラルウォーターのボトルは、使用する直前によく振ってください。
3. 上記2の中に、茶葉を入れます。
茶葉はご自宅にあれば、2種類(各大さじ1杯)入れてください。
なければ1種類(大さじ1杯)でもかまいません。
写真は、「さんぴん茶(ジャスミン茶)」と「烏龍茶」を使っています。
茶葉そのままでも、ティーパックでもOKです。

4. 出来上がった上記3は、ザルなどで漉して冷ましておきます。
冷蔵庫で冷やしていただいても構いません。

5. 上記4を冷やしている間にお茶碗、汁碗などの器に1/3程度のお好みのお茶を入れておきます。
ぶくぶく茶は二層式のお茶なので、これが下の層になります。
この上に泡を載せます。
正式には玄米を炒って煮出した玄米湯を使いますが、スペースの都合上、次回以降にご紹介しますね。
6. いよいよ泡立てです。
上記4に対して、茶せん、泡だて器などを手早く切るように大きく動かします。

茶せんで泡立てているところ

泡立て器で泡立てているところ
白い泡が立ってきます。
たっぷり泡立ったら、上記5の上に盛ります。

いい泡が立ちましたでしょうか?
初めて作って見事な泡を立てる生徒さんもいらっしゃいますが、私自身は始めた頃、なかなか泡を立てることができない生徒でした。
教授になり、何百回となく立てている現在でも、自分が満足できる泡を作れたことはありませんが、「ひとつひとつをおろそかにせず、自然への感謝を忘れずに」という恩師の言葉を胸に、日々皆様に福福茶を立てています。
みなさんも、ぜひ親しい方にぶくぶく茶を作って差し上げてくださいね。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

琉球茶道教室ぶくぶく茶館代表。
琉球茶道教授。沖縄ぶくぶく茶コーディネーター。
沖縄に渡り、家元・田中千恵子氏(蒼海伝統文化学院 理事長)に師事する。ヒューマンアカデミー那覇校、県立高校などで指導経験を積み帰阪。現在、関西を中心に活動中。
●ブログ
http://yaplog.jp/soukaidento/
●ホームページ
http://yaplog.jp/bukubukucha/
●メディア実績
http://yaplog.jp/soukaidento/archive/1134
●イベント実績
http://yaplog.jp/soukaidento/monthly/200001/
|
|
|