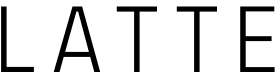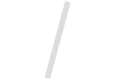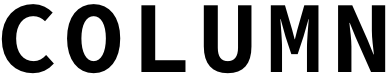日本酒の歴史と文化。お酒は巫女が噛んで作っていた!? -前編- (2/2)
鎌倉・室町・安土桃山時代における日本酒の歴史と文化
鎌倉・室町時代(1192年~)になると、早くも現在の清酒造りの原型が誕生。
下記のような様々な手法が「御酒之日記(ごしゅのにっき)」に記述されていてます。
- 「麹」と「蒸米」と「水」を、2回に分けて加える段仕込の方法
- 乳酸醗酵の応用
- 木炭での濾過方法
- 搾った酒を、貯蔵前に加熱、殺菌し、酵素の動きを止める「火入れ」

そして、自蔵で酒の醸造を行い、販売する店舗を持つ造り酒屋が、京都(主に伏見)を中心に隆起し始めました。
その後、安土桃山時代(~1600年)になると、十石入り仕込み桶が開発され、お酒の大量生産も可能になったのです。
御酒之日記とは、武家の佐竹氏に伝えられた、現存する日本最初の民間の酒造技術書。(Wikipedia引用)
おわりに
「日本酒の歴史と文化」前編は、安土桃山時代まで見てきましたが、いかがでしたか。
こうして見ると、人とお酒との関係は、非常に古の時代から築かれていたことが伺えます。
次回は「日本酒における歴史と文化」の後編をお送りしたいと思います。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア
コラムニスト情報

性別:男性 |
現在地:山梨県 |
日本酒利き酒師 純米狂@takezoです。
コラムでは、日本酒の素晴らしさを少しでもお伝え出来れば・・・と思っております。
日本酒の布教活動として毎月「純米狂の集い」という日本酒の会を地元山梨で主催しています。その会も今年で14年目に突入です♪ もし興味がある方はHPやブログに遊びに来て下さいね。
「純米狂公式HP」→ http://junmaikyo.com/
「純米狂@takezo 酔ゐどれ日記ブログ」→ http://junmaikyo.exblog.jp/
「キュレーションマガジン Antenna」で山梨代表キュレーターもしてます。→ https://antenna.jp/event/66
|
|
|