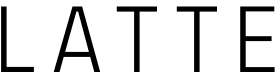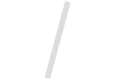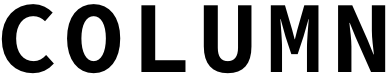「うつ病」と「抑うつ」における治療方法の違いとは?医師・カウンセラーの選び方 -後編-
こんにちは、心理カウンセラーの田中勝悟です。
前回「「うつ病」と「抑うつ状態」の症状と違いは?「うつ」を正しく理解しよう -前編-」では、同じ「うつ」でも「うつ病」と「抑うつ状態」は全く違うことをお話させて頂きました。
両者の共通点は「うつ症状」があるかないかです。
そして、日常生活に支障を及ぼしている「うつ症状」が改善すれば「うつ病」「抑うつ状態」は寛解(治った)ということになります。
今回は、その治療法についてお伝えしたいと思います。

「うつ病」の治し方は次の通りです。
薬を飲んで、栄養を取り、しっかりと安静にして身体を休めること。
もともと「うつ病」とは脳が疲弊し、脳内の神経伝達物質が正常に分泌されなくなった状態です。
だから気持ちが不安定になり、不眠や食欲不振、倦怠感、頭痛、胃痛などの「うつ症状」が表れます。
そこで、治療はまず脳内の神経伝達物質が正常になるようにお薬で調整することです。
さらに、栄養のあるもの(肉類、大豆、魚などのタンパク質、野菜がお勧めです。神経伝達物質の材料になります。甘いものや炭水化物は控えましょう)を食べ、その上でしっかりと休むこと。
その中で、脳のバランスも整われ、うつ症状は改善します。
これはストレスが原因なので、ストレスの対処法をしっかりと学ぶことです。
そのためには、カウンセリングが有効です。
カウンセリングで、ストレスの原因となっているものを整理し、どうなればストレスがなくなるかを考えて、実践していきます。
例えば、ストレスの原因が「イヤと言えなかったために、必要以上に回りから無理難題を押し付けられた」というのであれば、対処法は「上手なイヤの言い方」です。
このようにストレスの対処法が分かってくることで、ストレスの耐性が付き、それに伴い「うつ症状」は改善していきます。
実際、このやり方で私は多くの「抑うつ状態」で悩んでいる方をサポートしてきました。
ただ、これだけは伝えておく必要があります。
実際の「うつ病」「抑うつ状態」の違い、つまり脳内の異常が原因か、ストレスが原因かはベテランの医者でも見分けがつきにくいことが多く、また最初はお薬で症状を改善することが必要になる場合が多いです。
実際は「お薬で症状の緩和→その後で薬を併用しながらカウンセリング」の順番で、医療とカウンセリングを併用していくことが必要となるケースが多いです。
その中で症状が改善するにしたがって薬を減らしていき、最終的にはカウンセリング必要がない状態になることで治療が終わることになります。
もし、「うつ症状」が日常生活に影響が出るまで起こり、これって「うつ病?それともストレスが原因?」かと悩まれたら、一番安全なのは精神科医療に詳しいカウンセラーのもとを訪ねることです。
それが難しいようでしたら、心療内科・精神科のクリニックを受診すると良いでしょう。
その際、注意したいポイントは、医師がしっかりとあなたの話を時間をかけて聴いてくれるかどうかです。
もし、5分だけ聞いて「ああ、うつ病だ」といって理由も聞かずにお薬を処方されたら、その医師は警戒した方がいいでしょう。
ちなみに、優れたカウンセラーの見分け方は、「これは病院へ行った方がいいでしょうか?」「うつ病と抑うつ状態、どちらと思いますか?」と質問した時に、わかりやすく、あなたを害することなく、お話をしっかりと聴いた上で答えてくれるかどうかです。
「うつ病」に詳しくないカウンセラーであれば、これを聞かれると慌てふためいてしまいます。
以上、簡単ですが、「うつ病」と「抑うつ状態」の治療についてお話しました。
実際は両者はごっちゃになることも多いので、医療とカウンセリングを上手に併用していくことが望ましいです。
「うつ病」はしっかりと適切に治療すれば、必ず治る病気です。
治らないのは、例えばストレスが原因なのに、ストレスの対処法を考えずに、薬だけで何とかしようとするなど、不適切な治療をしている場合です。
ぜひ、これを読んでいる方が良き医者、良きカウンセラーにであることを心から祈って、筆をおきたいと思います。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

病院と学校で心理カウンセラーの仕事をしています。
多くの方の幸せに貢献できるようなカウンセラーをめざし、日々勉強中の身です。
少しずつ、成長しているのかな?と迷いながら前に進んでいるという感じです。そんな中で私が感じたことコラムでお伝え出来ればと思っています。
|
|
|