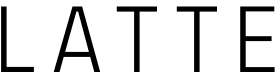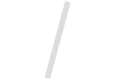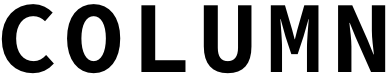部下や後輩が「うつ病」になった時の正しい対応とは?放置か病院への受診命令か…ストレスサインを見逃すな!
ストレスチェック義務化法が施行されるなど、職場のメンタルヘルス対策はもはや必須。うつ病など、社員のメンタル不調を予防する仕組みと対応について紹介。
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
平成27年12月から開始した、労働者が50人以上の事業場でストレスチェックの義務化には、次のような背景があります。
- 職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合が、高い状況にある。
- 精神障害の労災認定が、3年連続で過去最多を記録している。
私たち社会保険労務士が、傷病手当金の連絡を顧問先から受ける際も、圧倒的にメンタル不調が多いのが実情です。
せっかく入社してもらった従業員が、メンタル不調になり休職、または退職となってしまうのは、もったいないですね。
どうすれば、従業員のメンタル不調を防げるのか。
不調が疑われるときに、どのように対処するべきなのか。
少し考えていきたいと思います。

会社には従業員に対する安全配慮義務がありますので、事前に従業員の健康状態を知っておくことは大切です。
病歴がある従業員を採用し、何の配慮もしなかったために後々不調を招いてしまうということがないよう、採用時には、健康情報を収集しておくのがベターです。
そのためには、会社でフォーマットを決めてしまうと良いでしょう。
次のような項目を、はい、いいえの選択式で並べ、適時具体的な状況を記述で申告してもらいます。
- これまでの入院や手術歴
- 現在の通院の状況
- 過去の健康診断での指摘事項
- 過去や現在のメンタル不調歴
- 申告の趣旨を明確にしておきます。(入社選考の参考資料とする以外の目的で使用しない、など)
- 本人の署名をとりましょう。
- 虚偽の申請があった場合の対処は、あらかじめ明記しておきましょう。
メンタルヘルスケアの1つに、「ラインケア」と呼ばれるものがあります。
ラインケアは、管理職が部下のメンタル不調の予防や早期対応をして、必要に応じて専門家につなげることです。
管理職が日常的に声かけができるよう、管理職研修などで傾聴のスキルに関する研修を行っている会社もあるようです。
一般の従業員の身近な存在である管理職が、親身になり話を聴いてくれるのは、とても心強いことだと思います。

実際に、メンタル不調が疑われる従業員が出てきた場合は、どのように対処すれば良いのでしょう?
周囲が不調に気づき、病院への受診を勧めても、本人に「大丈夫です」と言い張られてしまう場合があります。
口頭で受診を勧めても受け入れない場合、書面で受診命令を出しましょう。
不調に気がついていながら、そのまま就業させてしまうと、後々会社が「安全配慮義務違反」を問われることもあります。
- 通常に勤務を続けることが危惧される、具体的な事例があれば記載しましょう。
- 会社には「安全配慮義務」が求められていることを明記しましょう。
- 診断書の提出を求めることはもちろん、期限も指定しましょう(※)。
- 就業規則に、受診命令について規定しておきましょう。
※受診命令の発令から、3日程度が妥当です。
ストレスチェックの受検勧奨もですが、「メンタル不調は特別なことではない」、「早めの対策が重要である」ということを伝え、メンタルヘルスケアへの理解を深めておくことが大切ですね。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|
|