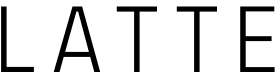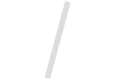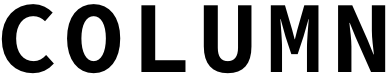マダイのいるポイントは?コマセマダイの釣り方コツ-「タナ」の位置とコマセ・ワーク- (1/2)
前回のコラムで、マダイの釣り方の一つ、コマセマダイで必要な道具についてお話しました。
今回は、コマセマダイの釣り方のポイントをお伝えします。

コマセマダイで重要なのは、釣り人によって違うかもしれませんが、やはり一番異論のない所で言えば「タナ(棚)」でしょう。
上の画像はある日のマダイ釣果ですが、マハタが混じっています。
「タナ」とは、魚のいる深さ(遊泳層)のことです。
ただし、コマセマダイでいう「タナ」とは、ビシダナといって、コマセカゴの位置(深さ)のことです。
コマセビシを使う釣りではどれも同じでしょう。
コマセマダイに限ったことではないのですが、「タナボケ」といって、これが合っていないと釣れません。
このタナの位置は、船長が教えてくれます。
アナウンスで「下からハリス分」とか言われれば、コマセビシを底まで沈めて、それが6mなら、そこからそのハリス分だけコマセビシをシャクリ(煽ってコマセを出す)ながら、6mほど巻き上げます。
「プラス何m」とか「ナイナス何m」と言われれば、それで巻き上げる位置を変えます。
東京湾では底からタナを取りますが、相模湾や駿河湾では「上から何m」とアナウンスされます。
その場合は、そのタナより数m(3mから6mくらい)コマセビシを沈めて、そこから指示されたタナまでシャクリながら巻き上げます。
上からビシダナを指示するのは、コマセビシが着底する音でマダイを警戒させないようにという理由からだそうです。
東京湾は海底の地形が変わるので下から取るのでしょう。
ところで、最近はデジタルカウンターの付いたリールが結構あります。
私は電動を使う時でも、あまりこのカウンターは信用していません。
多少狂います。
やはり、道糸の、1m、5m、10mごとに色分けされたPEラインでタナを決めましょう。
この方が正確です。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア
|
|
|