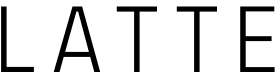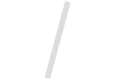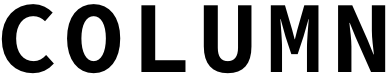筋肉をつけるには「たんぱく質」だけではダメ! たんぱく質以外に必要な栄養素とオススメ食材
筋肉づくりには「たんぱく質」が不可欠。でも、タンパク質だけでは筋肉を作ることはできません。筋肉をつくるために必要な栄養素や食べるべき食材、筋肉を落とさないための工夫など紹介。
こんにちは、アスリートフードマイスターの佐々智雄です。
私たちのからだを構成するたんぱく質。
もちろん「筋肉」も主に「たんぱく質」で組成されています。
食べ物から摂取された「たんぱく質」は、消化の過程で最終的には「アミノ酸」まで分解されて小腸から吸収され、肝臓から血管を経由して全身に運ばれます。
そして、それぞれの組織でアミノ酸から「たんぱく質」に再合成され、筋肉が作られます。

筋肉をつくるためには、たんぱく質以外にも必要な栄養素があります。
例えば、「たんぱく質の合成」にかかわる亜鉛やビタミンB群、コラーゲン生成に必要なビタミンCなどがあげられます。
「風邪をひかないように」とか「お肌のため」に「ビタミンC」をとる、ということは、よく耳にする話だと思います。
ですが、筋肉を作るためにビタミンCが必要だということは、意外に思われるかもしれませんね。
「コラーゲン」生成のために「ビタミンC」が大切ということは、特に女性はご存知の方が多いかも知れません。
細胞と細胞を結着する接着剤的な役割をもつ「コラーゲン」は、筋肉や、腱、骨などを構成する要素で、肌だけではなく、からだ作りには重要なものなのです。
そのコラーゲンを作るためにビタミンCが必要です。
体内でたんぱく質を効率よく合成するには、すべての必要な「必須アミノ酸」をバランスよく含む「アミノ酸スコアの『高い』」食品を摂取することが大切です。
肉や魚、乳製品など、多くの「動物性たんぱく質」を含む食材は、一部の魚介類を除きアミノ酸スコアは100のものが多いです。
一方、穀類、豆類、野菜などの「植物性たんぱく質」を含む食材はアミノ酸スコア100に満たないものが多く、唯一「大豆」が、最新の基準においては100となっています。
アミノ酸スコアが高いからと言って、肉や乳製品だけ食べていれば良い、というわけでありません。
できるだけ魚や大豆なども食べて、バランスよくとりましょう。
魚や大豆は、肉類だけではまかなえない他の栄養素を一緒に摂ることができます。
魚、とりわけ青魚に含まれるDHAやEPAなどの「オメガ3脂肪酸」は意識してとらないとなかなか摂取できません。
また、大豆に代表される豆類などの植物性たんぱく質からは、ビタミンB群、マグネシウムなどのビタミン、ミネラルも摂取できます。
また、肉食過多の場合に、動物性脂肪の摂取増が問題になります。
動物性脂肪は、丈夫な血管の材料となることから最低限は必要なものですが、摂りすぎは問題になります。
体脂肪増加、コレステロールの材料にも
体脂肪として蓄えられたり、コレステロールの材料にもなってしまいます。
肉を選択するなら、なるべく脂身の少ないものを選択するのが得策です。
また、リンなどを多く含む肉や乳製品の摂りすぎは、血液を酸性に傾けるため、血液を中和しようと骨からカルシウムを溶かし、血液中に放出させるような作用が働きます。
その結果、骨が弱くなることに繋がります。
「酸性食品」ばかりに偏らないよう、「大豆」などのアルカリ性食品と合わせてバランスよく摂りましょう。
アスリートが体を動かすためにエネルギー源としてもっとも使われるものは「糖質」です。
エネルギーが不足してしまった場合に、たんぱく質を分解する、言い換えると、「筋肉を壊して」エネルギーとして使ってしまうこともあります。
体を動かす量に見合った必要な糖質をしっかり摂取することです。
筋肉を落とさないためには、必要以上にたんぱく質をエネルギーとして使ってしまわないことも大切なのです。
単純に筋肉量がついていることの確認であれば、体重から体脂肪を除いた「除脂肪体重(LBM)」が増えていることを目安にすることができます。
育ちざかりのお子さんは別として、内臓や骨がほぼ成長しきった「大人」の場合、除脂肪体重の増減はほぼ「筋肉」の増減となります。
例えば体重が減り、体脂肪率が減っていたとしても、筋肉量が落ちているケースもあります。
体脂肪率ではなく、「除脂肪体重」で確認しましょう。
筋肉づくりに「たんぱく質」をたくさん摂取することは大事なことです。
ただし、食べられる量には限界があり、過剰に摂ることは肝臓や腎臓に大きく負担を与えます。
よい筋肉を効率よく作るためには、トレーニング後なるべく早く食事をとり、たんぱく質以外に必要な栄養素も、日頃からバランスよく食べることで体内に保持しましょう。
また、たんぱく源も「質」を考えて摂ることを心がけましょう。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|