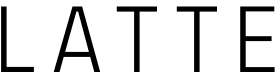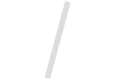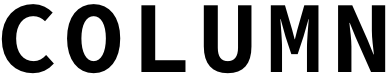黄帝内経から学ぶ、100歳まで健康的に長生きするためのコツとは
こんにちは。「葉山はり・きゅう接骨院」院長の葉山靖真です。
黄帝内経の「素問」(そもん)という文献に「上古天真論」(じょうこてんしんろん)という論文が記載されています。
これは、現代にも通ずる養生法を説いています。
こんな書き出しで始まります。
昔、黄帝あり。生まれながらにして神霊云々…
医学書なのに、まるで小説の書き出しのようで面白そうな気がしませんか?
その黄帝が、岐伯(きはく)先生に問います。
「昔の人は100歳になっても元気だった。今時の人は50歳になるともうヨボヨボだ。その理由を聞かせてくれ」
今回は、その質問に対して岐伯先生が答えた内容を紹介します。
現代にも通じる回答です。
好きだからといって、食べ過ぎてはだめです。
もっとも食欲のない時は、まず好きで食べたいと思う物から食べると、食欲が沸いてきます。
そのような方法を上手く使って、食を楽しみたいものです。
俗に言うストレスです。
最近、西洋医学でもその重要性に着目してきた心身医学が、この時代にあったのです。
怒り過ぎてイライラするとのぼせます。
のぼせると頭痛、不眠などになります。
高血圧症の人には特に悪いです。
あるいは、恋の病などで悩み過ぎると、必ず胃腸の消化力が低下します。
古典医学では、このような精神的動揺を病気の原因の一つに数えます。
怒り、思う、悲しみなど7種類あります。
七情(しちじょう)や内因(ないいん)と言われています。

お酒に酔うと身体が温まり、活動的になります。
古典医学ではこの状態を「陽気が多い」といいます。
酔いが覚めると、寒くなります。
これはお酒が覚めるときに、体内の陽気(熱気や活動力)が余分に取られているからです。
お酒を飲んで陽気を消耗する行為を行った後、酔いが醒めてさらに陽気を消耗します。
そのため、後日必ず身体がだるく、冷えて下痢をすることもあります。
これでは生命力自体が弱ることになりますので、身体に良いわけがありませんね。
これは前回伝えた内容です。
本論では年齢と成長過程との関係も記されています。
現代医学の考えと合うか、自分と比べてどうか確認してみて下さい。
- 永久歯が生え、髪が伸びる年。女は7歳。男は8歳。
- 男子は生殖能力が備わり、女子では月経が始まる。女は14歳。男は16歳。
- 知歯が生える。女は21歳。男は24歳。
- 最も充実した身体になる。女は28歳。男は32歳。
- 顔にしわが生じ、抜け毛が始まる。女は35歳。男は40歳。
- 白髪ができだす。女は42歳。男は48歳。
- 女は49歳で月経が閉止。男は56歳で身体全体が老化する。
- 男は64歳で歯も髪も抜けてしまう。

以上は平均的な話です。
このような養生法を守れば、確実に100歳まで生きられるそうです。
しかし、現代のように医学が発達していなかった中国の昔の人が、果たして本当に百歳まで生きられたのでしょうか?
実は、実際に100歳まで生きたと年齢が書かれた文献も、多数発見されているようです。
事実なだけに驚きですね。
参考文献 素問 ハンドブック/池田政一著
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|