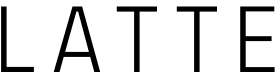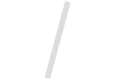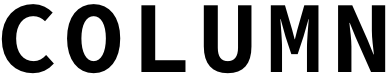Kotist(箏奏者)
日本の伝統楽器である「箏」の奏法や特色を大切にしながら、ポップスやロック等、 宮西希が今まで触れてきた音楽を融合させ、自身が書き下ろしたオリジナリティ溢れる楽曲を独特のスタイルで表現している。
伝統継承を重んじた従来の箏曲演奏とは一線を画し、自らをKotist(コティスト)と称して、グローバルな活動を展開している。
まるで数面の箏が合奏をしているかのように聴こえる“独奏”に特徴があり、メロディー、伴奏、オブリガードを十本の指が舞うように弾く宮西独特の奏法はダイナミックで迫力があり、聴衆の心を魅了する。
ギター、アコーディオン、ヴァイオリンとのセッション、そしてさらにピアノ、ウッド ベースとのJazzyなアンサンブルやロックバンドとのジョイントまで、その演奏スタイルは幅広く、自在にチューニングを変えることであらゆる楽器とのセッションにも対応でき、今までも多くのミュージシャンとの共演を果たしている。
また、身近なストリートから様々なスペースのコンサートホール、緑に囲まれた野外音楽堂まで演奏場所を選ばず、カジュアルな装いでの特製スタンドによる「立ったまま」の自由な演奏スタイルは、伝統的な和楽器を身近に感じさせ、箏という絃楽器の持つ優れた特性をフルに活かした『Kotist宮西希の世界』を実現している。
作曲から編曲まで自ら手掛けるインストゥルメンタル作品の数々は、美しさとエネルギーに溢れ、情景や心情を映し出し、まさに聴く人の琴線に豊かに響いてくる。これは、宮西の多くの楽曲がTV番組のBGMやコマーシャル音楽等に起用され、オンエアされている大きな要因ともいえよう。そして、その楽曲を紡ぎだす箏の音色は、聴く人の固定観念を打ち崩すほどにあたたかく、パワフルで、そしてとてもやさしい。伝統やしきたりにはこだわらない、全く新しい感覚をかね備えているニューエイジ・アーティストである。
また、観客からのジャンルを問わないリクエスト曲に答え、その場で即興演奏をするパフォーマンス(本人曰く「Kotoっちゃう」)が、大変人気コーナーとなっており、西洋音楽と純邦楽の両方の言葉と理論を熟知し、同時通訳できる音楽のバイリンガルとも評されている。
母の手ほどきにより箏を始め、3歳で初舞台をふむ。
東京芸術大学卒業後、日本、中国、韓国の3カ国の伝統楽器の代表奏者によって構成される楽団「オーケストラ・アジア」に参加。
SkyPerfecTV! 246ch.「ECO MUSIC TV」(制作:第一興商)の番組『eco music colors』で、自らが作曲したオリジナルのインストゥルメンタル作品が番組で採用。それをきっかけに本格的な作曲/音源制作を経て、2002年秋、アルバム『Steps to the Moon』(日本クラウン)発表、ソロアーティストとしてデビュー。
多くのアーティストやミュージシャンとステージやTV・ラジオ番組にてセッションし、2005年にはTBS「第47回輝く!日本レコード大賞」にアルパ奏者の上松美香とコラボレーションでゲスト出演、多方面から注目を集めた。
国内はもとより海外での公演も行ない、2006年にはAustraliaの在パース日本国総領事公邸に招かれた。ここでは、「Perth Royal Show」Japan Pavilionでのステージの他、公邸でのコンサートにも出演。各界から集まったたくさんの聴衆の歓心を得た。
その後も「多くの方々に箏の音色をより身近なものに感じてもらえるように」と、各地でのコンサートやイベント、ラジオ・テレビの公開放送、学校コンサートなどの他、教育の現場に招かれての授業・コンサート・進路講演等、様々なシーンに精力的に出演している。 現在も、WORLD NHKでは毎日のように「Sunset」がBGMとして使用され、海外に住む日本人からも大変好評いただいている。
2011年東日本大震災後は直後の4月から、1人で車を運転し東北へ向かい、避難所を訪れ音楽での支援を開始。そこでの「体に食料が必要なように、心にはエンタテインメントが不可欠」という体験をブログ等に綴るうち、ファンの方々から「活動の支援をしたい」との声が上がり「Music for Youプロジェクト」を発足。被災地訪問を続けている他、病院コンサートなどもこのプロジェクトとして行なっていく予定である。
2013年1月、待望の5枚目のアルバム「じゃぱねすけ」をリリース。東北の避難所で多くの方々が涙した「春紫苑~ハルジオン~」をはじめ、日本人としてのアイデンティティを意識して作られた「じゃぱねすけ」「SAMURAI Z」「京都へ」など自らプロデュースした曲の他、アレンジ・プロデュースにギタリスト天野清継氏を起用し、さらに広がりを増したアルバムに仕上がっている。すでにTVなどでも日々ON AIRされており、今後の活動が期待されるアーティストである。
|
|
|