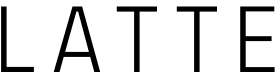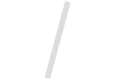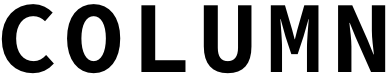薬の効果は思い込み!?医薬品の「プラシーボ効果」と副作用の関係
こんにちは、プラセボ製薬の水口直樹です。
効くと思い込めば、たとえ薬効成分を含まない偽薬(ぎやく)でも効いてしまうような現象を説明する言葉として「プラシーボ効果」が良く知られています。
また逆に、副作用があると言われて飲めば、偽薬でも好ましくない事象を引き起こすことがあり、これを「ノシーボ効果」と呼ぶことを前回のコラムでご説明しました。
さて、今回の本題はここからです。
プラシーボ効果やノシーボ効果は、偽薬だけにあるものなのでしょうか?

実は、プラシーボ効果やノシーボ効果は、偽薬だけにあるものではありません。
プラシーボ効果以上の効果、すなわち「真の効果」を持つとされる“ホンモノ”の医薬品にもプラシーボ効果があります。
“ホンモノ”とされる医薬品でも、こうした思い込みの力と薬理学的な作用の相乗効果で身体に影響を及ぼしています。
もちろん科学的に認められた“ホンモノ”の医薬品ですから、その「真の効果」たるや、もちろんプラシーボ効果よりも顕著である、そんな風に考えていませんか?
実は、この「真の効果」とプラシーボ効果をはっきりと分けて考えることは出来ません。
統計を用いて何とかその差(=「真の効果」)を見出すことしかできないのです。
また、その差(=「真の効果」)は「差がない、とは言えない」差であればよく、プラシーボ効果よりも顕著か否かは全く問題にされません。
したがって、「ある“ホンモノ”の医薬品の効果の大部分はプラシーボ効果だ」ということも起こり得ます。
かつて“ホンモノ”とされていた医薬品の内、改めて効果を検討してみると、プラシーボ効果以上の効果がなかったために販売が停止された医薬品が存在しています。
しかし、そうした“非ホンモノ”とされた医薬品でも当の患者や治療に用いていた医者は効くと信じていましたし、実際に効果の実感があったようです。
「真の効果」がプラシーボ効果よりも顕著であるとすればおかしな話ですが、プラシーボ効果がその「真の効果」の実体だったとすれば納得のいく話ではないでしょうか。
“ホンモノ”の医薬品にプラシーボ効果があるように、もちろんノシーボ効果もあります。
医薬品を投与する際の副作用の説明義務は、医療倫理的に当然必要と考えられています。
ですが、副作用の説明を読んで、「副作用が出る」と思い込むノシーボ効果の影響を受け、より強調された形で副作用が現れてくる可能性があります。
医療倫理とノシーボ効果の兼ね合いは、まだまだ議論が進んでいません。
薬の作用とプラシーボ効果は切っても切れない関係です。
プラシーボ効果に関する研究が、今後の医療観や健康観をより良く変えてゆくものと期待しています。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|